■一般部門 審査詳細
今年の審査結果の特徴は、“差がほとんどない”ということです。全体のクオリティはかなり高いので、“粒が揃っている”と言う方が的確かもしれません。
例年、審査員は各方面の専門家を集めています。ですから、各審査員の視点が異なるため、採点結果が大きく異なり、その採点結果を合計すると、どの作品も似たような点数になって差が付かない…ということが、過去何度かありました。
しかしながら、今年の場合、各審査員の採点結果自体、どの作品も同じような点数になっており、ほとんど差がついていません。ですから今年の場合、単純に“差が無かった”ということで問題ないと思います。
応募者の皆さんは、入賞、入選、選外といった審査結果を非常に気にされるのですが、審査員の目からすると、少なくとも本審査に残った作品については、あまり大きな違いがあるようには見えません。(本審査に残らなかった作品には、かなり差がありましたが)
実際、選外になった作品の中にも、入選どころか、賞に推された作品もいくつかありました。そもそも、本審査に残った作品は、皆レベルが高く、例年だったら、入選はもちろん、佳作ぐらいになってもおかしくない作品ばかりだったと言えます。
そのような状況のため、本審査では、一人で2作品応募されている方や、作風や方向性が似ている作品は、“どちらか一方に絞ろう”という心理が働いたように感じられます。
そういった、“例年だと確実に入選していただろう作品”の何本かは、外伝に収録しました。かなり見応えのある作品もありますので、ぜひご覧下さい。
なお、上記のように、今年は優れた作品が多かったため、入選作品の量(総尺)を若干多くしました。また、外伝も一緒に収録するために入選作品集DVDを2層化しました。
さて入賞等ですが、グランプリについてはほとんどの審査員の方が、“突出した作品はないので、グランプリは無し”という判断でした。また他の審査員もグランプリに推薦する作品がすべて異なっていました。ですから、グランプリに関する議論はまったくなく、早々に“該当作品なし”となりました。
■採点結果(100点満点)
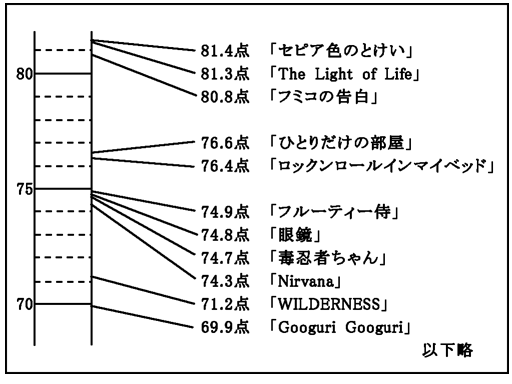
賞や佳作は、単純に採点結果の上位から決めました。
上記のグラフのように、上位作品が3群に分かれています。そこで、80点台の3作品を入賞、70点台後半の2作品を佳作としました。
「フルーティー侍」〜「Nirvana」も佳作にするという案もありましたが、入選17作品の過半数(9作品)が入賞・佳作ということになり、多すぎると判断しました。
ちなみに、入選作品の最低点は、68.2点でした。入選と選外のボーダーライン上に、作品が密集していたことがご想像頂けるかと思います。
◆一般部門 総評
以下、審査員の方々の総評を抜粋しました。(順不同)- すべての作品が同一列に並んでおり、たいへん悩ましい審査でした。あと少しだけ工夫すると、もっとよくなることが見えているだけに、とても惜しい作品が多々ありました。作品をつくる上でのよき指導者とめぐりあってほしいと思います。
- 力作ぞろいでした。いわゆる商業アニメーションとは別なところで、これだけの作品が生み出されていることに驚きました。ただ、“これがCGなの?”という部分で迷うところが多く、審査は難しかったです。
- 完成度があると感じた作品は、作家性、ストーリー、意外性など、どこかにしっかりと軸がある。時間や予算など制限がある中で制作されたと思いますが、もっと突き詰めてもらうと面白いものができると思います。
- 最終審査作品の中には、言葉を文字にして出す作品がしばしば見受けられたが、その必要性が明確ではないものが少なくなかった。漫画に色と音をつけて平面的に動かしたところで、読者が自分の「間」で楽しむ漫画には及ばない。
- どうやって作っているのかわからない作品が増えてきた。伝統的なアニメや、漫画など他のメディアの手法も活用し、様々な方向性を模索することは歓迎する。
さらに今回は腐女子の好きそうな作品も出現し、ジャンルの広がりとその個別の協調性が伺える。新たな転換期を迎えようとしているのかもしれない。 - アート的な作品はもちろん、ストーリー性のある作品でも、視覚で説明することを心がけてほしい。ナレーションやセリフに頼るのではなく、キャラクターのしぐさや表情、背景やその色使い、さらにはそれを観客に伝えるためにはどれだけの間が必要か、等々。
そういう意味で残念な作品があったように思います。 - 自主製作である事がプラスに出ている作品はやはり強い。実験的でありながらも焦点を絞り込み、独自の世界観と持ち味を存分に打ち出す作品も沢山あった。
自分が学生だった頃と比べると、映像の完成度は驚くほかない。
ただ、優れた作品が生み出され続けていく為にも、クリエイターの発掘と共に、観客層を広げることも進めるべき課題だと思う。 - 仕事柄、ついつい人月工数や製品レベルでの評価をしがちなのを、頑張って“こんなCGアニメ作品を作りたい!と思わせられる作品”をテーマに審査させて頂きました。
全体的にはレベルは高く、更に悩みは深まるばかりでしたが、評価している時間は楽しかったです。
多少厳しく評価してしまった作品も、個人的には好きなものも多く、CGがこれだけ自然に表現方法として確立していることに驚愕しつつ、次代を担う人達に何かが残せそうな予感がしました。 - CGは、アニメを作るための手段であるので、どこまでCGなのかはあまり気にしなかった。それは、作者にしか分からない面もあり、作者自身が、制作の多くをPC上で行ったというのなら、CGアニメといってよいのではないか。
全体的なレベルは極めて高かったが、グランプリが出なかったのは残念だ。それは、上位作品でも、ストーリーとかテーマとか、弱いところがあるからだろう。
そういった完璧さとは相反するが、完成度が低くても、自主制作CGアニメの新しい方向性を開拓するような作品をもっと見たかった。もっともそういった作品は、本審査に残っていないのかもしれないが。そういう点では、外伝も楽しみだ。
■初心者部門 総評
前回(第21回)から、初心者部門の応募が、激減しました。これは、前回から応募〆切が、2月14日から7月末に変更されたため、CG系専門学校等から、まとめて卒業制作作品を応募するということが無くなったためと思われます。
応募総数が少ないと、自然とよい作品も減り、今回初心者部門の入選は、9作品に留まりました。
やはり、初心者部門とはいえ、作品の体をなしていないもの、形にはなっていても何のアイデアや工夫もないものは、入選できません。
■初心者部門賞について
「初心者部門賞」については、最初から、「holiday!」、「KONPON!」、「なつのくに」の3作品に絞れていました。
「holiday!」、「KONPON!」は、完成度が高く、技術的にも優れており、すぐプロとして通用するレベルにあるでしょう。特に「KONPON!」はすばらしく、デザインや色のセンスは、一般部門でも通用しそうです。
その点「なつのくに」は、完成度が低く、習作の域を出ていない面もあります。しかし、クリエイターとして、“自分なりに表現したいモノを持っているか”、“それを自分なりに工夫して表現しようとしているか”という点で、他の2作を上回っていました。
もっと、わかりやすい言い方をすると、“これらの作品の作者が、来年一般部門に応募してきたとしたら、どの作品を見て見たいか?”と聞かれれば、それは「なつのくに」なのです。
初心者部門の目的は、将来性のある優秀な人材を発掘することでもあります。

