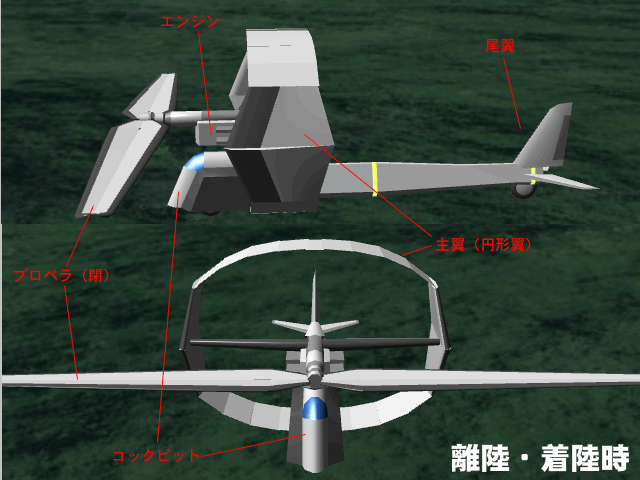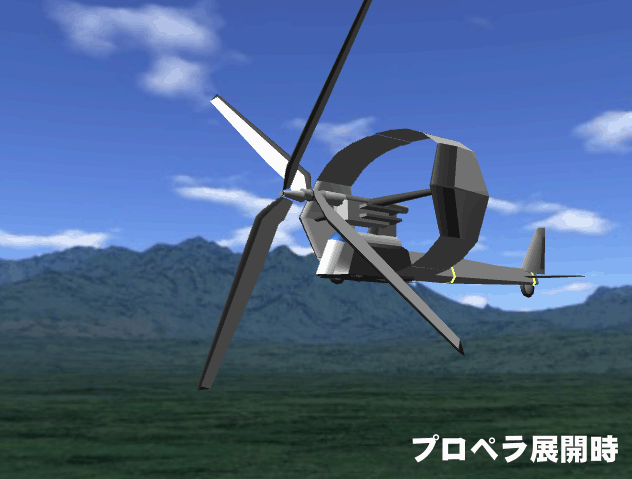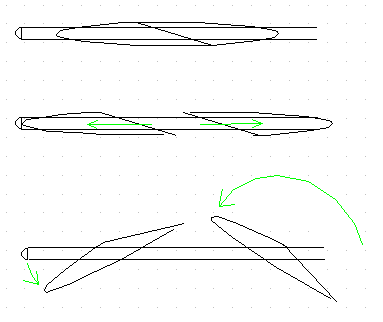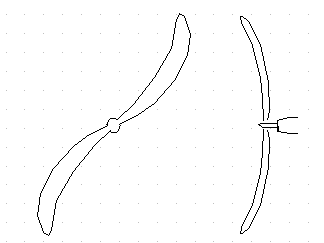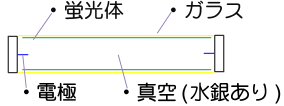 |
・蛍光灯は、その両端に電極があり、その間はほぼ真空(水銀などが入っている)になっている。
つまり、「+極」と「?極」はつながっていない。 ・その両端にある一定以上の電圧をかけると、電極間の放電(小さな雷)が始まり、電子の流れができる(=電流が流れる)。 ・蛍光灯のガラス(回路図では水色の部分)の内側には、蛍光体が塗ってあり、これに電子がぶつかると光る。よって、蛍光灯に電圧をかけると光る。 (厳密に言えば、電子がまず水銀原子にあたり、紫外線を出す。この紫外線が蛍光体にあたると光る。) |
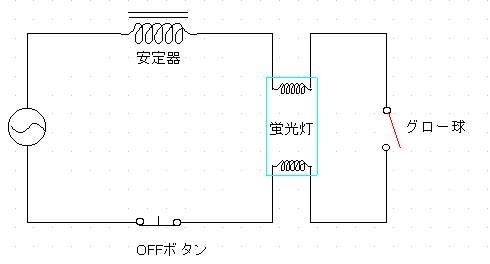 |
グロースターター回路とは、最初の放電を起こすために、瞬間的に電圧の高い状態を作るための回路。
(左図では、蛍光灯より右側の部分)
|
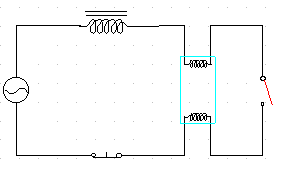 |
初期状態 |
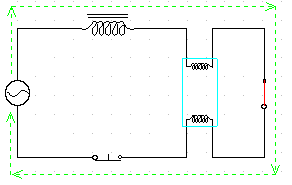 |
グローONまず、蛍光灯と並列に、電流が通る道を用意してやる。(緑の点線は、電流の流れ)
|
 |
グローOFF
すると、いままで流れていた電子達は、行き場を失って、一瞬電圧が高い状態になる。 |
 |
放電開始
|
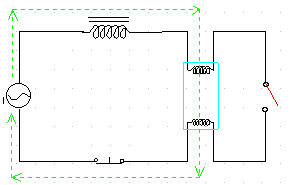 |
安定点灯 |
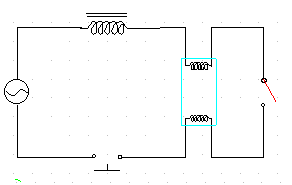 |
OFFスイッチいったんOFFスイッチを押すと、回路は途切れ、電流が流れなくなる。 すると、OFFスイッチをはなしても、そのまま
初期状態に戻る。 |