■一般部門 審査詳細
昨年の審査では、入選のボーダーライン上にたくさんの作品が密集して、甲乙の差が付けられず、非常に困りました。しかし今回は、グランプリから選外まで、割とばらつきがあり、そういう面では審査は楽でした。
ただ今年は、例年以上に“パーソナルCGアニメのあらゆる可能性を追求する”という指針を強め、意図的にいろんな方向性の作品を選びました。例年だと、欠点の少ない優等生的な作品が入選することが多かったのですが、今年の場合、多少欠点があっても、突出した点があったり、他の作品にはない方向性を提示する作品がいくつか選ばれています。
そのため、まったく異なる方向性の作品を同時に審査することになり、審査員の方々は、かなり苦労していました。
■採点結果(100点満点)
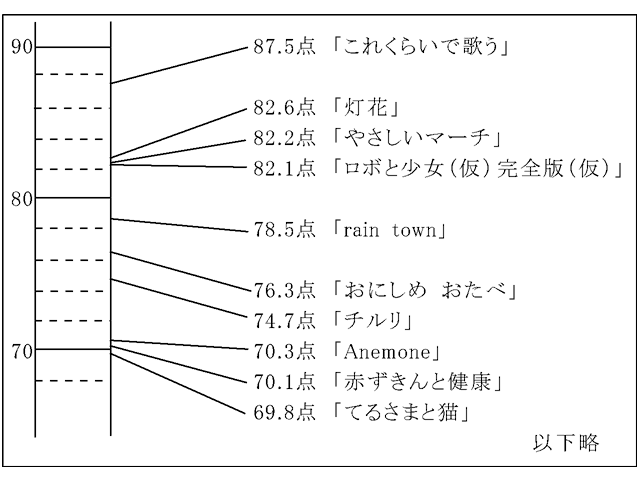
●グランプリ
今年は、実に6年ぶりにグランプリが出ました。
DoGA内で行われた予備審査では、グランプリの候補として、「これくらいで歌う」と「やさしいマーチ」が有力視されていました。しかし、本審査では、「これくらいで歌う」の方が、ほぼ全員の審査員から強い支持を得たのに対して、「やさしいマーチ」には若干名否定的な方がいらっしゃいました。その“万人受け”の差で「これくらいで歌う」がグランプリになりました。
映像でも、テーマ性でも、文句の付けようがなく、実にグランプリにふさわしい傑作だと思います。
●各賞
「灯花」、「やさしいマーチ」、「ロボと少女(仮)」が、点数的にきれいに揃ったので、この三作品を入賞としました。
「やさしいマーチ」は、「これくらいで歌う」と方向性がかぶる点があり、比較対象にされて、若干不利だった面があるように感じます。
「ロボと少女(仮)」は、昨年度も、第1、2話が入選していますが、連作にもかかわらず、そのクオリティや勢いを落とさず、むしろ盛り上げており、シリーズものとしての完成度が高く評価されました。
●佳作
点数的には、「rain town」だけでなく、「おにしめ おたべ」と「チルリ」も佳作にするという案もありました。
ただ、“賞をあげたい作品”に「rain town」を選ぶ審査員は多かったのに対して、「おにしめ おたべ」以下の作品への支持はあまりなかったので、佳作は「rain town」の一作だけにしました。
●入選
入選は、“物理的に上映会の時間内で上映できる量”で、ばっさりと切りました。
今年は、例年以上に尺の長い作品が多く、そのため、入選できる本数は少なめとなっています。
◆一般部門 総評
以下、審査員の方々の総評を抜粋しました。(順不同)●あまりにも違う方向性の作品を審査するのは辛かった。といいつつも、まだまだ他の方向性もあると思う。例えば、今回は純粋アート系の作品がほとんど無かったのが残念。
“なるほど、こういうのもアリだよな”という作品で、自主制作CGアニメの世界を広げてくれることを期待します。
●初めて審査に参加し、水準の高さに感動しました。本審査に残ったすべての作品は、技術的には価値あるものでしたが、その中でも、サプライズというか発見がある作品を高く評価しました。
このコンテストは、ぜひ多くの方々にご覧いただきたいと、強く感じました。
●売りどころを心得ている作品を選びました。
技術と語られる中身のバランスが取れているものを高く評価したが、総じて、語られる中身を託されたキャラクターが弱いように感じます。
内向きで、狭い視野の作品が多く、それならそれなりに、細部のリアリティで勝負して欲しいです。
技術面では、アクションの描きように物足りなさを感じます。
●水準は上がっているかと。長尺の作品も多く、作者のバイタリティには感心します。
独創的な作品が多い中、よりオリジナリティを追求した真実味のある表現を期待します。
●最終的には、ストーリーを重視した作品が残ったように思う。また、方向性が競合したため、厳しい採点になった作品もあった。
ただ、奇抜な作品が少ない中で、単なるエンターテイメントとは違う新たな分野への可能性が示されたことは、今後のCGアニメの進展に意義があると思う。
●オリジナリティのある作品、いわば一個人が命を削って制作する強
さと、はかなさを感じられるセレクションでした。見ている自分が、その両刃の剣の先に立っている緊張感がたまりません。
●今回もレベルが高く、採点にはかなり悩むことになりました。
表現については“商品”レベルであり、逆に「商品」には無い、制作者たちのメッセージが強く表現されていて、心地の良い刺激を体感する事ができました。
●以前と比べると、全体にストーリーをまとめることと、ストーリーのためにアニメーションするということが、噛みあってきた感じがする。その点をクリアしている作品が上位に来たと思われる。作品が作品らしくなる重要な部分が充足されてきたようだ。
表現に関しても、非常に細かいところまで演出に神経を払っているものが増え、そうでないものと水をあけた。
制作には、どんな分野でもフィニッシュワークというものがあり、送り出す前に、受け手の立場に立った最終チェックが必要である。自作を厳しい受け手の目でチェックする、そういう心構えを持って欲しい。
●破壊衝動とは異なる、非日常表現が多いが、これらは総じて言えば、“みんな退屈しているけど、一所懸命楽しいものを探している・・・”という感じか。わたしはそれが悪い傾向ではなく、むしろ原動力に思える。来年の作品には、また変化があるかもしれない。
●テーマやテイスト、形式が異なる作品を評価することが、いかに難しいかを実感した。
さすが最終選考に残った作品は、いずれも素晴らしかった。その中で、“独自の世界観を持っている作品”の評価を高くしたつもりです。結果としては、技術や構成、テーマなどの総合力とも一致したと思います。
日本に、これだけのクリエイティブな力があることは、大きな財産ですし、大きな可能性です。
作家の皆さんは、独りよがりはいけませんが、良い意味で審査結果や講評は気にせず、自分の表現を信じ、さらに力を高めていってほしいと思います。
■初心者部門 総評
初心者部門の中では、「veil」が頭一つ抜きん出ていました。
確かに完成度も低く、何を表現したいのかも、漠然としか伝わって来ません。それでも、自分独自の伝えたいものを持っていることは重要です。
また、各カットが美しく、技術や映像センスの面では、一般部門でも通用するレベルです。
初心者部門の目的は、将来性のある優秀な人材を発掘することなので、ぜひ次回は一般部門で入選して頂くことを期待します。

